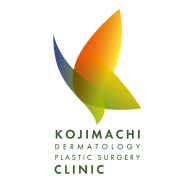- 【麹町皮ふ科・形成外科クリニック】(市ヶ谷/半蔵門/永田町/千代田区)
- お顔の治療
- アトピーと食事の関係性、食事療法で改善する?
- お顔の治療
アトピーと食事の関係性、食事療法で改善する?
2025.07.03
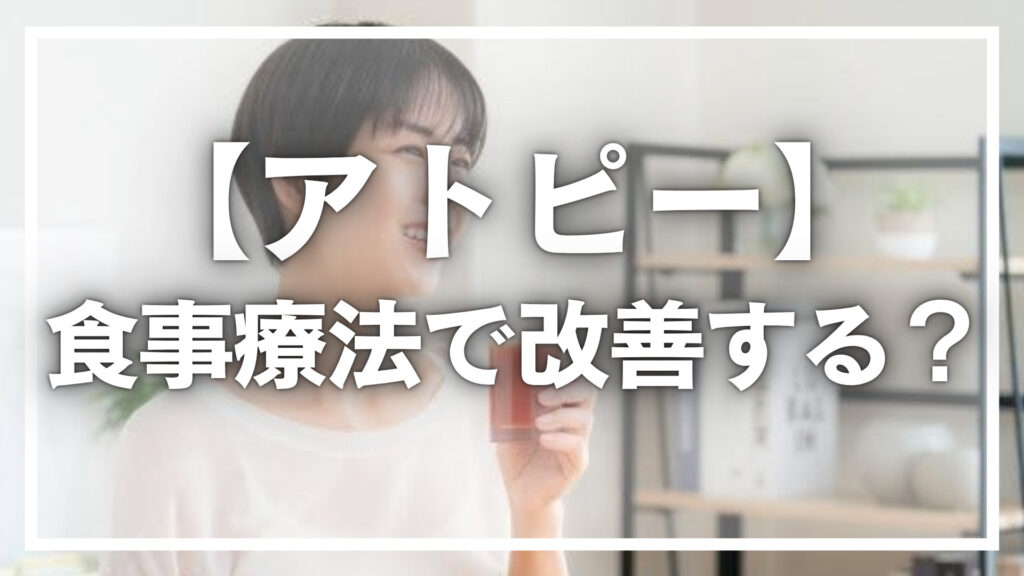
かゆみのある湿疹を繰り返すアトピー性皮膚炎。
アトピー性皮膚炎は、食事療法で改善すると言われているのです。
そこで本記事では、アトピー性皮膚炎の症状や原因、食事との関係性を紹介します。避けたほうが良い食べ物やおすすめの食べ物、食事療法の効果なども解説します。
最後におすすめのクリニックも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
アトピー性皮膚炎とは
アトピー性皮膚炎とは、かゆみのある湿疹を主な症状とした、良くなったり悪くなったりを繰り返す病気のことです。
皮膚の内側で炎症が発生し、皮膚が本来持っているバリア機能を低下させ、かゆみを引き起こします。
我慢できないほどのかゆみのせいで皮膚を掻いて壊してしまい、さらにバリア機能の低下と炎症を引き起こす悪循環に陥るのです。
アトピー性皮膚炎は、良くなったと思っても、またすぐに悪くなる場合があります。
なぜなら、皮膚の表面は綺麗になっても、炎症が皮膚の奥底に潜んでいるためです。
また、患者さんの多くが「アトピー素因」を持つとされており、アトピー性皮膚炎の診断の大きな判断基準となっています。
アレルギー性鼻炎や喘息を併発していることが多く、同時に治療することも少なくありません。
アトピー性皮膚炎の症状
アトピー性皮膚炎の症状は、かゆみのある湿疹が特徴です。
具体的には、赤くなる、赤いブツブツが出る、ジクジクした液が出る、ボロボロと皮がむけるなどといった症状です。
症状が長引くと、皮膚が硬くゴワゴワになっていきます。
かゆみのストレスからイライラしたり、精神的に不安定になったり、不眠症になったりする可能性もあります。
湿疹は体の左右対称にあらわれることが多く、顔や首、頭、ひじ、ひざ、お腹や胸から背中にかけてなどに出やすいです。
年齢とともに湿疹の出やすい部位は変わっていきます。
子どもは顔全体やひじ、ひざに出やすく、大人は額や目の周り、足首、手のひらに出やすいことが多い傾向です。
アトピー性皮膚炎の原因
アトピー性皮膚炎は、アレルギー疾患のひとつです。
ダニやハウスダスト、食べ物などアレルギーの原因となる物質が皮膚の内部に侵入し、炎症やかゆみを引き起こすと考えられています。
アトピー性皮膚炎を悪化させる要因は人によって異なりますが、複数の要因が重なり合って悪化するケースが多くみられます。
具体的には、汗やストレス、細菌・カビ、ダニ、ハウスダスト、食べ物などです。皮膚表面だけの問題ではなく、身体の内面の弱り乱れなどの「体質の崩れ」に原因があると考えられています。
アトピー性皮膚炎と食事の関係性
アトピー性皮膚炎の方の血液検査では、亜鉛やオメガ3脂肪酸の不足がよく見られます。
亜鉛やオメガ3脂肪酸は、皮膚の健康維持や炎症の抑制に重要な役割を果たしているのです。
また、かゆみを抑えるために必要な栄養素は、亜鉛やオメガ3脂肪酸以外にも、プロバイオティクスや抗酸化物質、水溶性食物繊維です。
また、肌のバリア機能を高めるビタミンも欠かせません。
また、腸内細菌のバランスが崩れてしまうと、アトピー性皮膚炎の症状を悪化させるリスクが高まると考えられています。
特に、善玉菌が減少して悪玉菌が増加することで、免疫の働きが乱れやすくなるのです。
アトピー性皮膚炎で避けたほうが良い食べ物
インターネット上で、「◯◯を摂取しなければ症状が改善する」と特定の商品を避けるように勧める情報をよく見かけます。
しかし、基本的には食物アレルギーのある方や医師から指示を受けた方以外は、特定の食品をまったく取らない方が良いということはありません。
ただし、体調の悪いときやかゆみが辛いときは、以下の食べ物を避けてみましょう。
| 避けたほうが良い食べ物 | 例 | 理由 |
| ヒスタミンを多く含んでいる食品 | ・動物性食品(鮭、サバ、イカ、えび、そば、豚肉など)
・植物性食品(ごぼう、たけのこ、ほうれん草、トマトなど) |
・かゆみを引き起こしたり、アトピー性皮膚炎の症状を悪化させる可能性がある |
| 刺激物 | ・アルコール
・辛い食べ物(唐辛子、キムチ、カレーなど) |
・血管を広げる作用があるため、発汗や皮膚のほてりを引き起こし、かゆみを悪化させる可能性がある |
上記の食べ物を避けたからといって、症状が絶対に改善するというわけではありません。
アトピー性皮膚炎におすすめの食べ物
アトピー性皮膚炎におすすめの食べ物は、以下の表の通りです。
| 栄養素 | 食べ物の例 | 効果 |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | ・脂肪が多い魚(マグロ、鮭、サバ、イワシなど)
・甲殻類 ・貝類(牡蠣、ムール貝、カニなど) |
・抗炎化作用があり、肌の赤みやかゆみを和らげる
・血流を改善し、炎症を抑える ・心血管の健康維持 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | ・海産物 | ・抗炎化作用があり、肌の赤みやかゆみを和らげる
・脳や神経の機能をサポートする ・記憶力や認知機能の維持 |
| ALA(α-リノレン酸) | ・植物油(亜麻仁油、えごま油、大豆油)
・ナッツ類 |
・抗炎化作用があり、肌の赤みやかゆみを和らげる
・体内でEPAやDHAに変換される |
| ビタミンA | ・にんじん
・ほうれん草 ・ピーマン ・レバー ・乳製品 |
・抗酸化作用
・皮膚や粘膜の健康維持 ・肌のターンオーバーを促進する |
| ビタミンC | ・じゃがいも
・さつまいも ・オレンジ ・グループフルーツ ・イチゴ |
・抗酸化作用
・免疫力の向上 ・皮膚や粘膜、血管、骨などの健康維持 ・メラニン色素の生成を抑制する |
| ビタミンE | ・ひまわり油
・大豆油 ・ピーナッツ ・アーモンド ・ブロッコリー |
・抗酸化作用
・血行促進 ・ホルモンバランスの調整 |
| カロテノイド | ・緑黄色野菜
・マンゴー ・海藻類(わかめ、昆布、ひじき) ・甲殻類(えび、カニ) |
・抗酸化作用
・皮膚や粘膜の健康維持 ・動脈硬化や老化の予防 |
| プロバイオティクス | ・発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチなど)
・甘酒 ・調味料(味噌、醤油、塩麹) |
・免疫力の回復
・腸内環境を整え、アレルギー抑制の効果がある |
| 亜鉛 | ・牡蠣
・豚レバー ・油揚げ ・卵 ・カシューナッツ |
・皮膚の再生
・免疫機能の維持 |
| 水溶性食物繊維 | ・海藻類(のり、わかめ、昆布)
・穀類(そば、オートミール、ライ麦パン) ・野菜(ごぼう、アボカド、にんじん) ・果物(みかん、キウイ) |
・便通を整える
・腸内細菌のバランスを整え、腸内環境を良好に保つ |
上記のものを偏って摂取するのではなく、バランスの良い食事をとることがおすすめです。
アトピー性皮膚炎への食事療法の効果
アトピー性皮膚炎への食事療法は、バランスの取れた食事が重要であると考えられています。
特定の食べ物を摂取することが、治療に直接的に効果があるわけではありません。
患者さんごとのアレルギーや体質に応じて、食事のバランスを調整することが大切であると言われています。
アトピー性皮膚炎はさまざまな要因が関係しているため、食事療法は薬物療法の補助として行うべきとされています。
もし特定の食べ物が関与していることが分かったとしても、特定の食べ物だけでアトピー性皮膚炎が完治するわけではないため、注意しましょう。
アトピー性皮膚炎のそのほかの改善法
アトピー性皮膚炎の改善法は、食事療法だけではなく、生活習慣の改善と肌への保湿ケアもあわせて行うことで改善すると言われています。
それぞれ、詳しく説明します。
生活習慣の改善
アトピー性皮膚炎は、生活習慣によって症状が大きく左右されやすいと言われています。
治療をしていても良くならない場合は、生活の中に潜んでいる悪化原因を取り除きましょう。
ダニやハウスダストなど
気密性が高く通気性の悪い現代の住宅では、住宅内部に空気や湿気がこもりやすいです。
ダニやハウスダストが増殖しやすいため、アトピー性皮膚炎の患者数が増加している一因となっていると言われています。
特に、子どものアトピー性皮膚炎はダニやハウスダストの影響が大きいと言われています。
住んでいる環境によって症状が左右することもあるため、通気性を良くしたり、掃除をこまめに行ったり、除湿をしっかり行ったりすることが重要です。
乱れた食生活
食生活の乱れは、アトピー性皮膚炎の症状に影響を与えると言われています。
たとえば、外食や偏食による栄養バランスの乱れや、ダイエットなど極端な食事制限による栄養不足などです。
また、甘い物や肉類、油、脂肪の多い食事なども、アトピー性皮膚炎の症状を悪化させやすいと言われています。
毎日の食生活を見直し、バランスの良い食事を心がけましょう。
ストレス
精神的なストレスも、アトピー性皮膚炎を悪化させる原因のひとつです。
心身医学的な側面が3つあり、以下の通りになります。
ストレスで皮膚炎が悪化する場合
強いかゆみや皮膚症状が原因で精神的に追い詰められて、不眠になったり人に会いたくなくなったりする場合
薬への不安や医療への不信感、症状がよくならないことなどから、医師の指示を守らなかったり、自己判断で治療を中断したりする場合
以上の3つは、相互に関連しあうことが多いと考えられています。ひとりで悩みを抱え込まずに、皮膚科の医師へ相談することが大切です。
肌への保湿ケア
アトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能が低下することで乾燥肌になります。
炎症が発生すると、皮膚のバリア機能がさらに低下するため、より乾燥肌が進んでしまうのです。
アトピー性皮膚炎の治療で使用されることの多いステロイド外用薬やタクロリム外用薬は、炎症を低減させる効果はありますが、保湿力はほとんどありません。
つまり、アトピー性皮膚炎の治療では、「皮膚の炎症を治療する外用薬」と「乾燥肌を治すための保湿ケア」の両方が重要になります。保湿ケアをする際のポイントは、以下の2点です。
保湿薬の種類
保湿薬には、さまざまな種類が存在します。
白色ワセリンなどの油脂は保湿薬の基本で、べたべたした感触ですが、刺激がほとんどなく保湿効果が高いと考えられています。
尿素製剤は、炎症がある部分に塗ると刺激を感じますが、べたつきにくいことが特徴です。ヘパリン類似製剤は、少し独特なにおいがありますが、べたつきにくく塗りやすいことがメリットです。
形状としては、外用薬やクリーム、ローション、泡タイプ、スプレータイプなどがあります。皮膚の状態に合わせて使うことがおすすめです。どのような種類を選べば良いか分からない場合は、皮膚科の医師に相談しましょう。
保湿薬の塗り方
保湿薬は、入浴を終えてから5分以内に塗ることが推奨されています。
皮膚が水分を保持している間に保湿薬を塗って、水分が逃げないようにするためです。入浴後すぐに皮膚が乾いてしまった場合は、化粧水などで皮膚を湿らせてから保湿薬を塗ると、効果が期待できます。
また、保湿薬は炎症が起きているところだけではなく、全身に塗ることがおすすめです。指先で塗るのではなく、手のひらに薬を多めにとって、しわにそって塗ると皮膚に広がりやすくなります。また、秋や冬など乾燥しやすい季節だけではなく、毎日継続するようにしましょう。
栄養療法なら、麹町皮ふ科・形成外科クリニック|BIOTOPE CLINICへ一度ご相談ください
アトピー性皮膚炎はアレルギー疾患のひとつで、かゆみのある湿疹が特徴です。
原因は人それぞれ異なり、汗やストレス、細菌・カビ、ダニ、ハウスダスト、食べ物などの複数の要因が重なって発症すると考えられています。
かゆみのストレスからイライラしたり、精神的に不安定になったり、不眠症になったりする可能性もある疾患です。
アトピー性皮膚炎を改善させるためには、食事療法だけでなく、生活習慣の改善や肌への保湿ケア、薬物療法などの方法があります。特定の食べ物を摂取すれば改善するわけではなく、バランスの良い食事、栄養をとることが重要です。
また、栄養療法が必要かどうかは、患者さんの症状によって異なるため、医師に相談することがおすすめです。
麹町皮ふ科・形成外科クリニック|BIOTOPE CLINICでは、栄養療法の相談を行っています。
電話や公式サイト、公式LINEから予約することが可能ですので、気軽に相談してください。
オーソモレキュラー栄養療法詳細はこちら
-
苅部 淳Karibe Jun理事長
-

-
- 略 歴
-
順天堂大学医学部卒業東京大学附属病院形成外科 入局埼玉医大総合医療センター 形成外科・美容外科 助教福島県立医大付属病院 形成外科寿泉堂総合病院 形成外科山梨大学附属病院形成外科 助教・医局長東京大学附属病院 精神科
- 専 門
-
日本形成外科学会形成外科専門医日本抗加齢学会専門医日本医師会認定産業医
- 専門分野
-
形成外科一般、マイクロサージャリー、リンパ管吻合術、乳房再建術、性適合手術、美容外科手術、静脈瘤、レーザー治療など。
美容外科手術、レーザー、ボトックス、ヒアルロン酸等
大手美容外科クリニックで長年にわたり研鑽を積み、形成外科専門医として医師の診療、指導にあたっている。
Categoryカテゴリー
Archiveアーカイブ
- 2025年11月 (13)
- 2025年8月 (4)
- 2025年7月 (5)
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (8)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (11)
- 2025年1月 (8)
- 2024年12月 (12)
- 2024年11月 (3)
- 2024年10月 (6)
- 2024年9月 (13)
- 2024年8月 (2)
- 2024年5月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年2月 (7)
- 2023年1月 (5)
- 2022年12月 (11)
- 2022年11月 (10)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (3)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (3)
- 2022年6月 (7)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (3)