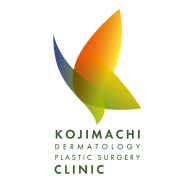- 【麹町皮ふ科・形成外科クリニック】(市ヶ谷/半蔵門/永田町/千代田区)
- 皮膚科
- ほくろ
- ほくろ除去を自分でするのはNG?リスクなど解説
- ほくろ
- お顔の治療
ほくろ除去を自分でするのはNG?リスクなど解説
2025.05.23
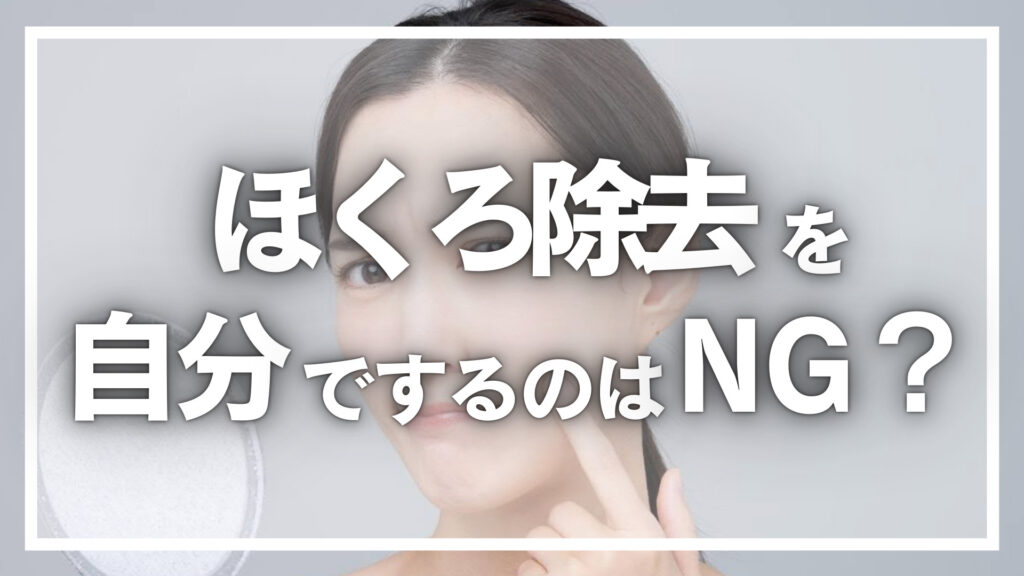
顔や体にあるほくろを「どうにか自分で取れないかな」と考えたことはありませんか?
忙しくてクリニックに行く時間が取れない、という事情もあるかもしれません。
でもちょっと待ってください!安易な自己処理は、想像以上に大きなリスクを伴う可能性が潜んでいます。
本記事では、ほくろ除去を自分でおこなうことの危険性や安全な除去方法について、詳しく解説します。
本記事を読むことで、自己処理の危険性を理解し、専門医に相談する重要性を認識できます。
あなたの大切な肌を守るために、ぜひ最後までお読みください。
ほくろとは
ほくろは皮膚に見られる小さな色素性の斑点で、一般的には褐色や黒色をしています。
医学的には色素性母斑(しきそせいぼはん)や母斑細胞性母斑(ぼはんさいぼうぼはん)と呼ばれ、メラノサイトという色素を作る細胞が増殖して形成される良性の腫瘍です。
生まれたときから存在するものもあれば、成長するにつれて新たに現れることもあります。
大きさはさまざまで、小さな点から直径数センチメートルを超えるものまで存在。
表面は平坦なものや盛り上がったもの、さらにはいぼ状のものがあり、毛が生えていることもあります。
ほとんどのほくろは良性でとくに治療の必要はありませんが、急に大きくなったり、形や色が変わったり、出血する場合は注意が必要です。
上記の症状がある場合は、悪性黒色腫(メラノーマ)との鑑別が必要です。
悪性黒色腫(メラノーマ)は早期の診断が重要であり、変化が見られた際には、皮膚科を受診し、専門医の診察を受けるようにしましょう。
ほくろの種類
ほくろは、大きく以下の3つの種類に分類されます。
後天性ほくろ
そのほかのほくろ
それぞれの種類の詳しい内容は、以下のとおりです。
| 先天性ほくろ | 詳細 |
| 先天性色素性母斑 | 生まれつき存在し、平坦なものから隆起したものまで形状が多様。直径20cm以上になる巨大な場合もあり、太い毛を伴うことが特徴 |
| 青色母斑 | 真皮の深層でメラニン細胞が増殖することによって形成され、青黒く見えるのが特徴。幼少期に出現し、成長とともにゆっくりと大きくなる。通常、平坦であり、周囲の皮膚と比較して色調が異なるため、視覚的に目立つ |
| 後天性ほくろ | 詳細 |
| Unna(ウンナ)母斑 | 主に顔や首に好発するほくろで、表面がデコボコした桑の実状の形状。直径は1cm程度で、色は黒〜茶色。やわらかい触感をもつ。紫外線や外部刺激によって形成されることが多い |
| Miescher(ミーシャー)母斑 | 顔や頭部に半球状に隆起する後天性のほくろ。色は黒〜茶色で、表面には光沢がある。加齢とともに肌色に近づく傾向がある |
| Spitz(スピッツ)母斑 | 若年者に多く、赤みを帯びた黒色。急激なサイズの変化がみられたときは、悪性黒色腫との鑑別が必要 |
| Clark(クラーク)母斑 | 中央が濃く周辺が薄いぼんやりした色素斑。胴体や手足に発生しやすい。平坦で、色調が均一であることが多いが、周囲の皮膚とのコントラストがあるため、視覚的に目立つ |
| その他ほくろ | 詳細 |
| 境界母斑(きょうかいぼはん) | 表皮と真皮の境界部分にメラノサイトが存在し、平坦で黒い色をしている |
| 複合母斑(ふくごうぼはん) | 境界母斑と真皮内母斑の混合型で、少し盛り上がった見た目をもつ |
| 真皮内母斑(しんぴないぼはん) | 母斑細胞が真皮内にのみ存在し、通常は薄茶色〜灰色の隆起したほくろ。真皮内母斑は加齢で隆起し、毛を伴うことが多い |
| 異型母斑(ディスプラスティックネバス) | 形状が不規則で直径6mm以上。メラノーマリスク(悪性黒色腫)を発症する可能性が高い。通常のほくろとは異なり、境界が不明瞭で、色調が不均一であることが特徴 |
とくに注意が必要な種類は、悪性黒色腫(メラノーマ)です。
一見ほくろのように見えますが、悪性度の高いがんのため、一刻も早い治療が必要となります。
以下の特徴が現れた場合に、悪性黒色腫(メラノーマ)が疑われます。
境界が不明瞭
色調の不均一
急速な大きさの変化
出血やかゆみ
とくに足底のほくろは日本人のメラノーマの40%を占めるため、上記の症状が見られた場合、すぐに病院で受診してください。
ほくろとシミの違い
ほくろとシミは、見た目が似ているため混同されがちですが、いくつかの重要な違いがあります。
ほくろは一般的に、母斑細胞(メラノサイトの変異細胞)が皮膚の真皮や表皮に集まって形成される良性腫瘍で、黒色〜茶色の隆起したものです。
一方シミは、紫外線や炎症などで表皮にメラニン色素が過剰に沈着した状態で、平坦で褐色〜茶色のものが多いです。
以下に、それぞれの特徴と違いを詳しく説明します。
| 特徴 | ほくろ | シミ(老人性色素斑) |
| 形状 | 隆起する・毛が生える | 平坦 |
| 色調 | 黒~茶色(均一) | 淡褐色~濃褐色 |
| 大きさ | 1mm~1cm(多くは5mm以下) | 数mm~数cm |
| 発生層 | 真皮・表皮 | 表皮 |
| 出現時期 | 先天性/後天性(全年齢) | 主に30歳以降 |
| 発生原因 | メラノサイトが変化した母斑細胞の増殖 | メラニン色素の沈着(紫外線、加齢、生活習慣など) |
| 治療法 | 医療機関での除去が必要 | セルフケアや美容皮膚科での治療レーザー治療など) |
| 触感 | 盛り上がっているため、触ると固い感触がある | 平坦で滑らか、触るとやわらかい感触がある |
| 注意点 | 急激な変化があれば悪性腫瘍の可能性あり | セルフケアで悪化する場合がある |
ほくろは、遺伝的要因やホルモンの影響を受ける場合が多く、とくに妊娠中や思春期に新たにできるケースもあります。
シミは、主に紫外線の影響を受けて発生し、日焼けを繰り返すことで増加する傾向があります。
シミの種類には、日光の浴びすぎによる、日光性角化症(にっこうかくかしょう)や肝斑(かんぱん)などがあり、それぞれ異なる治療法が必要です。
ほくろの診断は、主に皮膚科医による視診とダーモスコピー検査によって判断します。
ダーモスコピー検査とは、ダーモスコープという拡大鏡を使用して、ほくろの内部構造や色素の分布を確認します。
ダーモスコピー検査により、ほくろであるかの判別のほか、良性のほくろか悪性のメラノーマかを見分けることが可能です。
ほくろの原因
ほくろの発生原因は、遺伝的要因と環境要因が複合的に作用しています。
主な原因を、以下のように分類できます。
| 原因 | 説明 |
| 遺伝的素因 | 生まれつきほくろが多い体質は遺伝子によって決定され、家系に影響される。とくに大型のほくろは先天的要因が関与する |
| 紫外線曝露 | UV照射がメラノサイトを活性化し、メラニン生成を促進。肌の色が薄い人ほど紫外線の影響を受けやすい。 |
| ホルモン変動 | 妊娠・出産期や更年期の女性ホルモンの変動が色素細胞を刺激。月経周期に伴うほくろの色調変化も観察される |
| 物理的刺 | 日常的なメイク時の摩擦や衣服による圧迫が特定部位のメラノサイトを活性化。イヤホンの長時間使用で耳周辺にほくろが生じることも |
| 生活習慣要因 | 睡眠不足や栄養バランスの乱れが新陳代謝を阻害。ビタミンC・E不足がメラニンの分解機能を低下させ、ほくろとなる場合がある |
| 加齢現象 | 紫外線を浴びすぎた結果、主に40歳以降からほくろとして出現。年齢とともにメラノサイトが沈着し、ほくろを形成する |
| ストレスと生活習慣 | 日常生活でのストレスや睡眠不足、偏った食生活が新陳代謝を阻害し、メラニン排出のサイクルを崩すことがある。そのため、ほくろができやすくなることが知られている |
環境が要因でできるほくろの対策としては「SPF30以上の日焼け止めを年間通して使用すること」「抗酸化物質を豊富に含む食事」「22時前の就寝習慣」がおすすめです。
ほとんどの場合は良性ですが、急に大きくなる・色が変化する・周囲がにじむなどの異常を感じた場合は、念のため皮膚科専門医の診察を受けてください。
ほくろ除去を自分でするのはNG!
ほくろを自分で除去するのは非常に危険であり、絶対に避けるべきです。
自己除去には、以下のリスクがあります。
やけどの跡が残る可能性がある
ほくろが再発する可能性が高い
悪化のリスクがある(とくに皮膚がんの場合)
たとえば自分でほくろを針やカッターで切除することは、化膿や感染症のリスクを高めるだけでなく、最悪の場合、皮膚が壊死する恐れもあります。
ネット上で販売されている「ほくろ除去クリーム」も、重大な皮膚障害を引き起こす可能性があるため、使用は避けるべきです。
また、不完全な除去により再発し、かえって目立つ状態になるリスクも少なくありません。
上記のリスクを避けるため、ほくろの除去は必ず専門的な知識と技術をもつ医療機関でおこなうようにしましょう。
クリニックでは、切開法、電気メスによるくり抜き法、炭酸ガスレーザー治療などの安全な方法でほくろを除去します。
決して自分でほくろを除去しようとはせず、気になるほくろがある場合は皮膚科や美容皮膚科で相談することをおすすめします。
医師がほくろの状態を確認し、適切な治療方法を提案してくれます。
ほくろ除去を自分でするリスク
ほくろを自分で除去することには、深刻なリスクがあります。
以下に主なリスクを詳しく説明します。
| リスク | 詳細 |
| 医学的リスク |
|
| 皮膚がんのリスク |
|
| 美容的リスク |
|
自分でほくろの除去をおこなうと、一時的な解決ではなく、永久的な問題を生む可能性が高いです。
気になるほくろがある場合は、必ず皮膚科専門医の診断を受けることが最善の選択肢となります。
クリニックでのほくろ除去方法
クリニックでのほくろ除去方法には、従来のメスを使用した切開法と電気メスやレーザーを使用した治療があります。
それぞれの特性やほくろの状態に応じて、治療法が選択されます。
以下に、詳しく解説していきましょう。
手術
ほくろの除去手術には「切開法」と「くり抜き法」があります。
それぞれの特徴は、以下のとおりです。
| 除去方法 | 詳細 |
| 切除法(切除縫合法) |
|
| くり抜き法 |
|
両方法とも、深い根をもつほくろにもアプローチが可能なので、再発のリスクが低いことがメリットです。
ただし、深く切開するほど傷跡が残る可能性が高くなります。
どちらの方法を選択するかは、ほくろの大きさ、深さ、位置などによって異なります。
ほくろの除去手術は、医師の技術や経験が重要なので、信頼できる病院に相談することが大切です。
電気メスやレーザー治療
ほくろ除去の電気メスやレーザー治療は、従来の切開手術に比べて、手軽で効果的な方法です。
主な特徴は、以下のとおりです。
| 方法 | 詳細 |
| 電気メス治療 |
|
| CO2レーザー(炭酸ガス)治療 |
|
| ピコスポット |
|
電気メスとレーザー治療ともに局所麻酔を使用するため、施術の痛みはほとんどありません。
切開しないため皮膚への負担が少なく、施術後当日から洗顔やメイク、入浴が可能です。
レーザー治療の注意点としては表面的なアプローチとなり、ほくろの根が深い場合は完全に除去できないため、再発のリスクがあります。
深い根をもつほくろの場合は、確実に除去できる切除法がおすすめです。
ほくろでお悩みの方は、麹町皮ふ科・形成外科クリニック|BIOTOPE CLINICへ一度ご相談ください
ほくろに関する悩みをお持ちの方は、ぜひ麹町皮ふ科・形成外科クリニックにご相談ください。
専門医が丁寧に対応し、最適な治療法を提案します。
Co2レーザー(ほくろイボ取り)詳細はこちら
-
苅部 淳Karibe Jun理事長
-

-
- 略 歴
-
順天堂大学医学部卒業東京大学附属病院形成外科 入局埼玉医大総合医療センター 形成外科・美容外科 助教福島県立医大付属病院 形成外科寿泉堂総合病院 形成外科山梨大学附属病院形成外科 助教・医局長東京大学附属病院 精神科
- 専 門
-
日本形成外科学会形成外科専門医日本抗加齢学会専門医日本医師会認定産業医
- 専門分野
-
形成外科一般、マイクロサージャリー、リンパ管吻合術、乳房再建術、性適合手術、美容外科手術、静脈瘤、レーザー治療など。
美容外科手術、レーザー、ボトックス、ヒアルロン酸等
大手美容外科クリニックで長年にわたり研鑽を積み、形成外科専門医として医師の診療、指導にあたっている。
Categoryカテゴリー
Archiveアーカイブ
- 2025年11月 (13)
- 2025年8月 (4)
- 2025年7月 (5)
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (8)
- 2025年3月 (8)
- 2025年2月 (11)
- 2025年1月 (8)
- 2024年12月 (12)
- 2024年11月 (3)
- 2024年10月 (6)
- 2024年9月 (13)
- 2024年8月 (2)
- 2024年5月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年2月 (7)
- 2023年1月 (5)
- 2022年12月 (11)
- 2022年11月 (10)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (3)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (3)
- 2022年6月 (7)
- 2022年4月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (3)